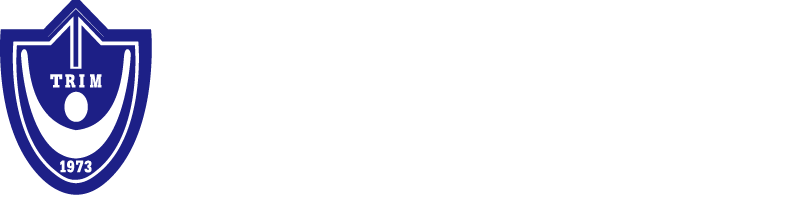ごみ処理設備大手のタクマが、間伐材などを使う木質バイオマス発電プラントで出た灰を肥料化する技術開発に取り組んでいる。
灰が肥料になれば新たな収入源になり、運営事業者の負担も減る。
技術開発部開発課の井藤宗親主幹(43)は、業界トップシェアを誇る木質バイオマス発電プラントのさらなる普及にもつながると期待を込める。
木質バイオマスプラントは2012年の再生可能エネルギー買い取り制度(FIT)を機に普及が進んでいる。
しかし、プラントから出る灰は産業廃棄物として処理されることがほとんど。
処理費用は運営費用の1割に上り、発電事業者の重荷となっている。
タクマは、この課題を解決するため「灰を畑にまくという当たり前で古典的な方法に着目した」(井藤氏)。
排出された灰には肥料成分であるカリウムが含まれているためだ。
ただ、そのまま肥料にするには濃度が足りない。
そこで2014年度、粉の選り分けに強みをもつ広島大学大学院や製材大手の中国木材(広島県呉市)など「灰を有効に使いたい」と考える5団体の担当者でチームを組んだ。
井藤氏は2015年度からチームに加わり、中心的な役割を担った。
西日本を中心に5カ所のバイオマス発電プラントに足を運び、灰まみれになってプラントを調査した。
灰の成分は燃料やプラントの種類によっても異なる。
粒子の大きさもさまざまだ。
井藤氏は採取した灰を分析したが、「正解が見えない生みの苦しみがあった」という。
各地のプラントに通ううち、発電事業者が灰の再利用に苦心している実態も見えてきた。
ある事業者は灰を再利用するために建材メーカーに持ち込んだが、断られていた。
井藤さんは自分たちが目指すものが「事業者と話すたびに必要とされている技術だという実感が高まった」と話す。
約1年かけて100種もの灰を分析した結果、粒子が小さいほどカリウムの濃度が高いことが判明した。
直径10マイクロメートル前後の細かい粒子のみ取り出す濃縮装置の開発に着手した。
異なる大きさの粒子を選り分け、必要な粒子のみを取り出すため、流速を調整した遠心分離機などを組み込んだ試験プラントを構築。
宮崎県日向市で実施した実証実験では、1日2.4トンの灰から700キログラムの肥料向けの灰が生み出せることを確認した。
一連の成果を基に2017年3月期にも商品化する計画だ。
タクマのバイオマス発電プラントの歴史は古く、1号機は1959年にさかのぼる。
井藤さんはもともと入社4年目の2001年から灰の研究をしていた。
トウモロコシやコーヒー、下水汚泥など、さまざまな物質を燃焼させた灰の成分を研究していたことが、今回の技術にも生きた。
タクマは木質バイオマス発電プラントの売上高を、2016~2018年3月期の3年間に、2013~2015年3月期の3年間に比べて2倍の600億円に引き上げる目標を掲げている。
同社のボイラープラント事業分野の技術部門の人員は、FIT開始前に比べて1.7倍の100人規模に増えた。
灰の活用は「これまで誰もが必要と思ってきたが実現できてなかった技術」と井藤氏。
全社を挙げて取り組むテーマの最先端を担っている。
【西岡杏】
日経産業新聞より